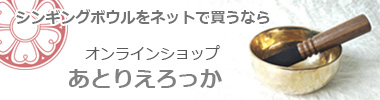ダラムサラ、3日目。
昨日お参りできなかった、カーラチャクラ堂へ。
そして、ミラクルが起きる・・・!
カーラチャクラ堂、ふたたび
この日も、本格的に雨。

おかしいなぁ、
わたし、晴れ女なんだけどなぁ(笑)
さて。
リベンジのカーラチャクラ堂です。
カーラチャクラ、というのは、時輪金剛(じりんこんごう)と呼ばれる仏さま。
密教の発展に伴って、
血に充たされた頭蓋骨杯や、切り取られたばかりの人間の首、
象の生皮や蛇といった不気味なものに飾られた恐ろしい姿の尊格があらわれました。
それはヘールカ(秘密仏)と呼ばれます。
カーラチャクラは、このヘールカの一人で、
「カーラ」は時間、「チャクラ」は輪を意味し、
時間のサイクルを象徴した尊格といわれています。
カーラチャクラは二十四本の腕と四つの異なった色の顔をもち、
それぞれの頭には三つの目をもってます。
また、両腕で彼のパートナー(ヴィシュヴァマーター)を抱いた姿で立っています。

こちらの写真は、2009年に上野の森美術館で開催された
「ポタラ宮と天空の至宝」のカタログからご紹介しています。
カーラチャクラ堂内は、残念ながら、写真撮影禁止。
入ってすぐに、立体曼荼羅があり、
壁一面にいろんな仏さまが描かれています。
その中心に描かれているのが、カーラチャクラ尊(時輪金剛)。
入口右手には、仏母二十一尊(21体のターラ菩薩像)が。
堂守のお坊さまが厳しい方だとかで(笑)
小さな声でしかお話できません。
思い思いの場所で、みなさん、静かに瞑想したり、
祈りを捧げたりしていました。
それが、なんというか、胸に迫った。
静寂。
いのり。
大切にする、ということ。
大切にされている、ということ。
ここの時間と空間をみんなで守っている、ということ。
それらが質量をもって、手渡された感じ。
カーラチャクラ堂を出た途端、
胸がいっぱいになって、泣けて泣けて仕方がなくて、
子供みたいに、うわぁん、と泣いていたよ(笑)
ミラクルが起こる
カーラチャクラ堂をぐるっと回って、出口に向かった時のこと。
お坊さまたちが、あわただしく行き来していて、
柱にマリーゴールドの花がぶら下げられていて・・・
法王さまと同じゲルク派のお坊さんだった、ロサンさん、
そして、長いこと仏教を学ばれてきた直子さんが、
「あ、この雰囲氣、もしかして・・・」と、
状況を確認したところ。
なんと、法王さまの体調が回復されて、
明日の儀式(プジャ)に参加される、
という情報が!(嬉)
ロサンさんと直子さんが、早速、場所とりのマットを敷き始めまして。
いや、法王さまは、この道を通るはず。
そして、いまこの早い時間だったら、最前列が抑えられる。
場所取りのマットを取りにいって、
そこに「Japan Team」の張り紙をして・・・
そんなこと、このふたりじゃなかったら、できなかったことよ(笑)

マットを敷いて、おのおの場所を確保します、が、
このマット、どこから出てきたんだろう・・・(笑)
たしかに、謁見はできなかったけれど、
最終日のプジャに参列できる!
法王さまに直にお目にかかれる!
もう、ミラクル~!(笑)
ロウアー・ダラムサラへ
参列の準備を整えて、ランチを食べたら、
午後は、ロウアー・ダラムサラへ。
チベットの亡命政府を訪ね、ペンパ・ツェリン首相にお会いしました。
写真で見るより、ずっと背が高くて、かっこいい(←そこ?笑)

亡命チベット中央政庁(CTA)

議員の数は、45名。議会は年に2回、開催される。
チベットの3つの地方から、それぞれ10名ずつ議員が演出され、
そのうち最低でも2名は女性候補でないといけない、とか、
現在、7つある大臣のポストのうち、
「治安」「教育」「情報・国際」の3つポストを女性の大臣が占めている、とか。
おりしも、日本では、初の女性総裁が生まれそうだ、
というニュースが。
そう考えると、本当に日本って・・・、むぅ・・・
印象的だったのは、教育をとてもとても大事にしていること。
そして、子供を教育する役割を担っている女性を大事にしていること。
チベットのこれからを背負っていく人材を失わないように。
自分たちのことを考えているんじゃないんだよね。
100年先のことを考えている。
そのためにどうしたらいいか、いま何ができるか。
チベットの人たちを知れば知るほど、
なんだか、昔の日本人が持っていた美徳を感じる。
はにかみ、謙虚さ、ひとに対する思いやり。
子供や未来を守る強さ、100年スパンの視点。
本当の智慧。
ツェリン首相に、思い切って質問してみた。
「ここにいる人は、チベットのことが好きで、
チベットのことをもっと知りたいと思っています。
これからも日本とチベットが仲良くしていくために、
わたしたちに期待することは何ですか?」
答えは、
「日本とチベットは、氣持ちの上ではとても仲が良いんだけれども、
具体的な支援の話になると、前に進みません」
実は、チベットを支援する団体は、日本が一番大きいんだそう。
政党を超えて、国会議員による「チベット問題を考える議員連盟」というものもある。
でも、この議員連盟は反中を掲げているわけではなく、
日中友好議員連盟にも加盟している議員も参加している。
国と国とのおつきあいは複雑だ。
ツェリン首相は、質問の中の「わたしたち」を「日本」に置き換えて答えてくれたけれども、
じゃあ、「わたし」は何を期待されているだろう?
わたしは、何ができるだろう?
ここが、メンツィーカン・・・!
最後に、チベット医学暦法研究所「メンツィーカン(Men-Tsee-Khang)」を訪問。

学校と博物館、診療所、ショップがあります。
博物館では、実際に、昔の四部医典(ギュー・シ)を見せてもらったり、
チベット医学で使われている器具の説明を聞いたり。
撮影NGなので、写真がないのが悔やまれるけど。

May I become the doctor,the medicine,and the nurse,
all who are sufferng ,until every being is healed.
と、看板に書いてある。
これは、チベット仏教の「菩薩の請願」の一節。
「どうか私が、すべての苦しむもののために、
医者となり、薬となり、看護するものとなりますように。
すべての命が癒されるその日まで」
原文は、シャーンティデーヴァが記した「入菩薩行論」の第3章。
「May I be a doctor and medicine, And may I be a nurce
For all sick beings in the world
Until everyone is healed.」

診療所の受付

こちらは、薬局。丸薬を購入するには、医師(アムチ)の処方箋がいる。
それにしても、なぜ、医学と暦法(占い)なの?
チベット医学では、人間も自然のめぐりの中の1つ、と考えるので、
手術をする日や薬を飲む日など、暦を見て決めるんだとか(驚)
なんと。

営業時間の終了ギリギリに、ショップへ。
メンツィーカンでは、チベット医(アムチ)に診断してもらい、処方してもらう丸薬の他に、
処方箋なしでも買えるハンドクリームや薬草茶、お香なども販売されている。
ちなみに、お香は、日本のお香と違って、ちょっといがらっぽいです(笑)
室内で香りを楽しむというより、場所を清めるために使うみたい。
お寺でもお香を焚いていたけれど、
日本のように、ずーっと焚いているものではなくて、
朝だけとか、お坊さまがいらした時だけ焚くんだって。

わたしは、花粉症にいいという「ARU BALM」と、
喉にいいというお茶を購入~♪
ほんわりハーブの香りがして、常用したい(笑)
他にも、アンチ・リンクルクリームが大人氣でした(笑)
これらのクリームなどは、タシデレさんでも一部とり扱っていますし、
メンツィーカンのオンラインショップもありますよ(笑)
夕方、ついに雨が上がって、
遠くヒマラヤの山が照らされていました。

ダラムサラ編(6)「金の種」に続きます!
シンギングボウルのふるさとを訪ねて ダラムサラ編
(1)いざ、インドへ!
(2)ダラムサラへの道
(3)リンポチェのお話
(4)ツクラカン・コンプレックス
(5)ここがメンツィーカン!
(6)金の種
(7)チベタン・アート
(8)修行と瞑想とシンギングボウル
(9)苦難の先に
(10)観音さまに呼ばれて
(11)旅の終わりはいつも
シンギングボウルのルーツを訪ねて ネパール編はこちら